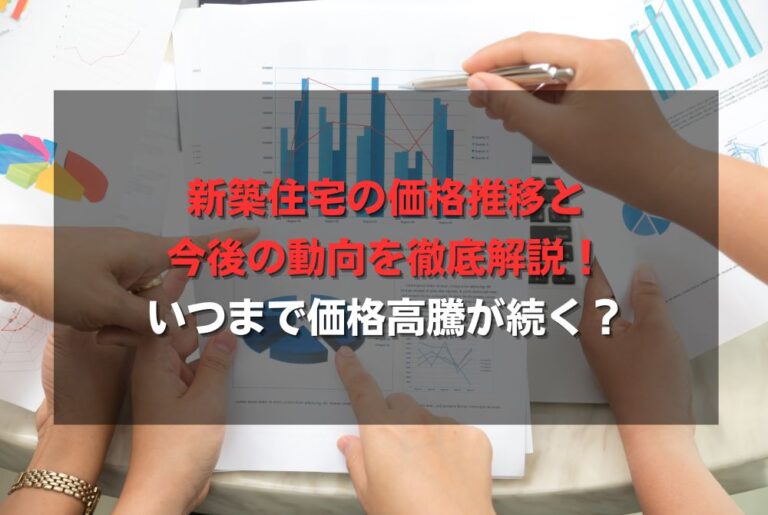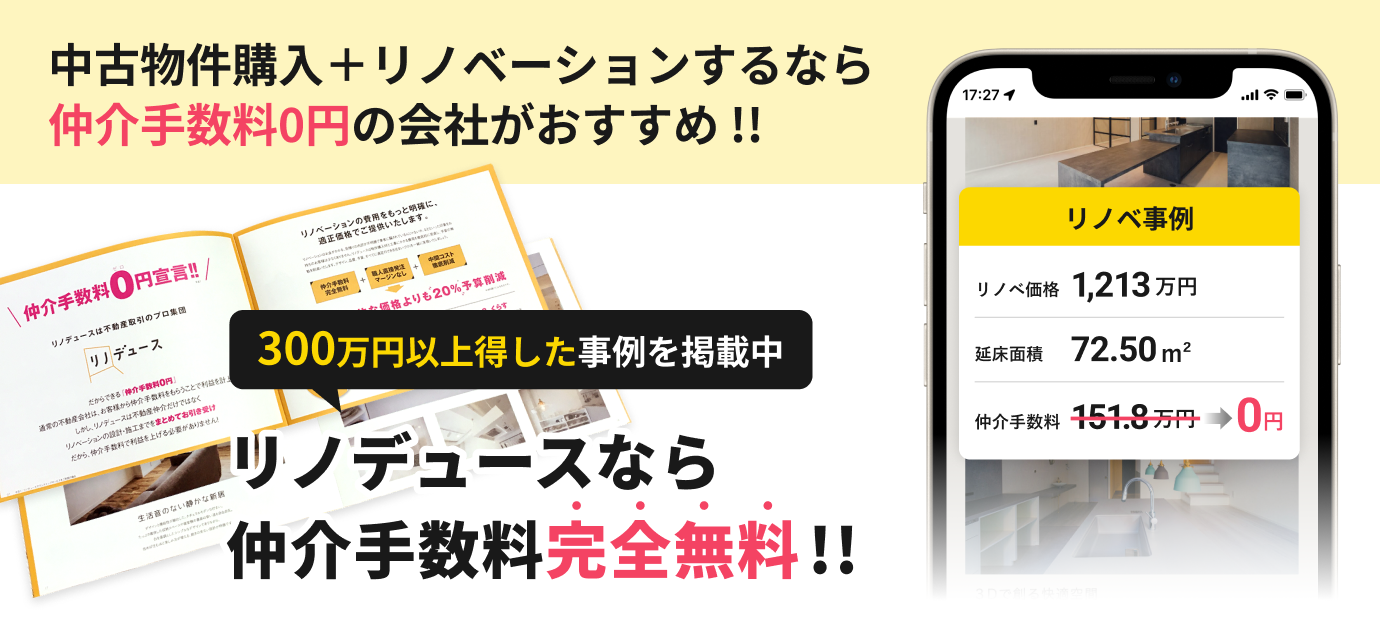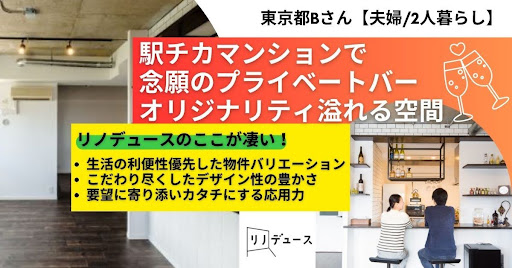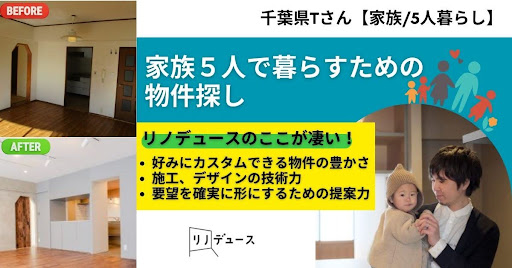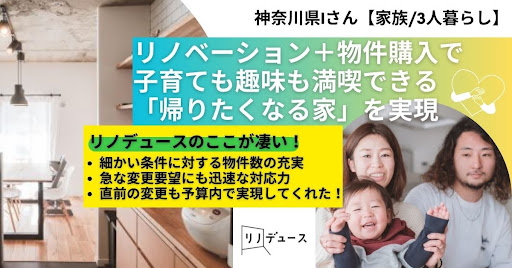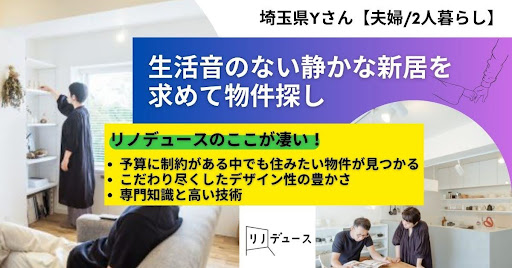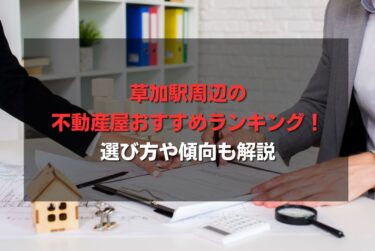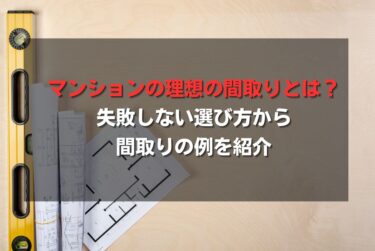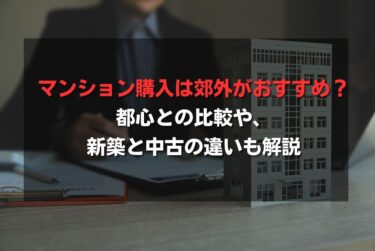住宅の購入や売却を考えているものの、高騰する住宅市場でいつ行動すべきか悩んでいませんか?
建築資材や人件費の高騰、円安、住宅ローン金利の動向など、様々な情報が錯綜し、最適なタイミングを見極めるのは難しいと感じる方も多いでしょう。
この記事では、新築・中古の一戸建てやマンション、土地それぞれの価格推移の現状と高騰の背景を詳しく解説します。
この記事を読むことで、今後の住宅価格の動向と、購入・売却の最適なタイミングを理解し、あなたの不動産売買の判断に役立つ情報が得られるはずです。
リノベーションとセット購入で
お得に理想の住まいを
実現しませんか?
- 今なら中古購入+リノベで仲介手数料0円!
- 完全オーダーメイドで理想の住まいを実現!
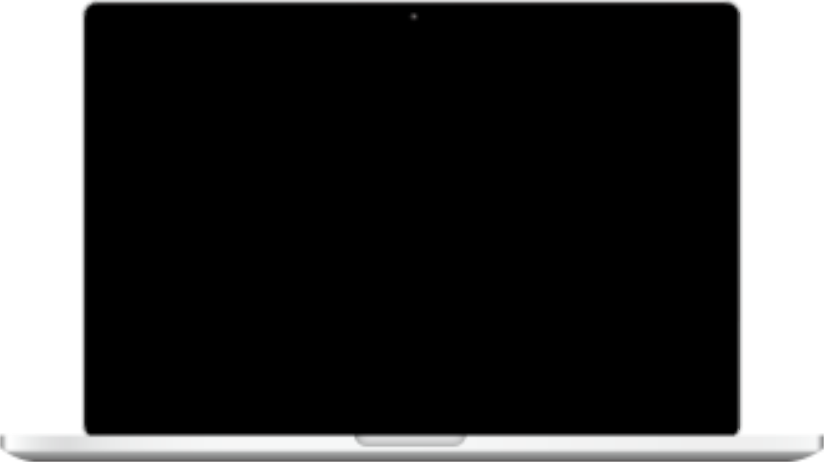
- 今なら中古購入+リノベで仲介手数料0円!
- 完全オーダーメイドで理想の住まいを実現!
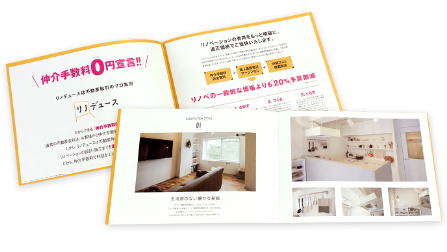
新築住宅の価格推移の現状

建築資材や人件費の高騰に加え、円安などの複合的な要因が加わり、近年、住宅価格は上昇傾向にあります。
このような市場環境の中で、新築住宅の購入を検討されている方にとって、その価格がどのように推移しているのか、また今後の動向はどうなるのかを理解することは非常に重要です。
ここでは、新築一戸建てと新築分譲マンションそれぞれの価格推移と変動傾向について詳しく見ていきます。
◉ 分譲マンションでは7年連続の上昇
一戸建て価格の推移と変動傾向
首都圏における新築一戸建て住宅の価格は、全体として上昇傾向にあります。
過去には前年比で価格が下落した年もありましたが、特に2021年と2022年には大幅な価格上昇が見られました。
しかし、2023年には前年比で価格は低下しています。
このような価格変動の背景には、建築資材や人件費の高騰、円安の進行が複合的に影響していると考えられます。
特に建設業界では、職人の高齢化や人手不足が深刻であり、人材確保のための採用コスト増や高い給与水準が建設費を押し上げ、最終的な販売価格に転嫁されています。
また、ウクライナ情勢やコンテナ料金の上昇、円安などが建築資材や住宅設備の価格高騰に拍車をかけています。
さらに、金融緩和政策によるインフレの進行や、低金利が続く住宅ローン金利も、購入者がローンを組みやすい状況を作り出し、借入額の増加を通じて住宅価格を押し上げる要因となっています。
なお、公益財団法人東日本不動産流通機構の調査によると、首都圏における新築一戸建ての成約価格の推移は以下の通りです。
| 年 | 価格(万円) | 前年比(%) |
| 2013 | 3,416 | -0.1 |
| 2014 | 3,447 | 0.9 |
| 2015 | 3,414 | -0.9 |
| 2016 | 3,522 | 3.1 |
| 2017 | 3,537 | 0.4 |
| 2018 | 3,468 | -2.0 |
| 2019 | 3,510 | 1.2 |
| 2020 | 3,486 | -0.7 |
| 2021 | 3,902 | 11.6 |
| 2022 | 4,128 | 5.8 |
| 2023 | 4,070 | -1.4 |
引用:公益財団法人東日本不動産流通機構 首都圏不動産流通市場の動向(2023年)
分譲マンションでは7年連続の上昇
全国的に新築マンションの販売価格は上昇傾向にあります。
特に全国平均では、価格が11年連続で上昇し、1平方メートルあたりの単価も7年連続で上昇して、1973年の調査開始以来、最高値を記録しました。
2023年の全国平均価格は5,910万円で、2022年から789万円増加(前年比15.4%増)と大幅に上昇しています。
なかでも首都圏の上昇が目立ち、前年比28.9%増と高い伸び率を示しました。
新築分譲マンションの価格が上昇している背景には、建築資材や人件費の高騰、円安の進行などがあります。
さらに、金融緩和によるインフレと、それに伴う不動産投資の増加が需要を支えています。
また、住宅ローン金利が低水準であるため、購入者が融資を受けやすく、住宅価格の上昇を後押ししています。
株式会社不動産経済研究所の調査に基づいた、全国の新築分譲マンション(全国平均)の成約価格の推移は以下の通りです。
| 年 | 全国平均(万円) | 首都圏(万円) | 近畿圏(万円) |
| 2014 | 4,306 | 5,060 | 3,647 |
| 2015 | 4,618 | 5,518 | 3,788 |
| 2016 | 4,560 | 5,490 | 3,919 |
| 2017 | 4,739 | 5,908 | 3,868 |
| 2018 | 4,759 | 5,871 | 3,844 |
| 2019 | 4,787 | 5,980 | 3,866 |
| 2020 | 4,971 | 6,083 | 4,181 |
| 2021 | 5,115 | 6,260 | 4,562 |
| 2022 | 5,121 | 6,288 | 4,635 |
| 2023 | 5,910 | 8,101 | 4,666 |
引用:株式会社不動産経済研究所 全国 新築分譲マンション市場動向 2023 年
新築住宅の価格が高騰している理由

ここでは新築住宅の価格が高騰している理由について解説していきます。参考にしてください。
◉ 円安による価格高騰
◉ 人件費による価格高騰
木材の価格高騰
新築住宅の価格高騰の主な要因の1つに、木材価格の高騰があります。
新型コロナウイルスの流行により、在宅時間が増加し住宅需要が高まったことで、木材の需要が急増しました。
一方で、パンデミックの影響で木材の生産や流通が滞り、供給が需要に追いつかない状況が発生しました。
この需給バランスの崩れが木材価格の高騰を招き、結果として新築住宅の建築コストを押し上げることになりました。
さらに、世界的な木材不足も価格上昇に拍車をかけています。
米国や中国などの大国での住宅需要の増加や、環境保護の観点からの伐採規制なども影響し、国際的な木材市場が逼迫しています。
コロナ禍による需要増加と供給制約、そしてグローバルな木材市場の動向が複合的に作用し、木材価格の高騰を引き起こしています。
その結果、新築住宅の価格上昇につながっているのです。
円安による価格高騰
円安の影響による建築資材の価格上昇も理由のひとつです。
日本の住宅建築業界は、木材をはじめとする多くの建築資材を海外から輸入しています。
そのため、為替レートの変動が直接的に建築コストに影響を与えます。
特に2022年には円ドル相場が一時150円台を記録するなど、急激な円安が進行しました。
この円安により、輸入建築資材の価格が大幅に上昇し、結果として新築住宅の価格を押し上げる要因となりました。
円安の影響は木材だけでなく、金属製品や石油由来の建材など、幅広い資材に及びます。
これらの資材価格の上昇は、建築業者のコスト増加につながり、最終的には消費者が購入する新築住宅の価格に反映されることになります。
このように、為替相場の変動、特に円安傾向は、新築住宅の価格高騰に直接的な影響を与える重要な要因の1つとなっています。
今後も為替動向には注意が必要であり、住宅購入を検討している消費者にとっては、為替相場の動きも価格変動の指標として見ておく必要があるでしょう。
人件費による価格高騰
人件費の上昇も価格高騰の要因です。
近年、建設現場での人手不足が深刻化しており、これに伴い労働者の賃金が上昇しています。
特に熟練工の不足は顕著で、技術を持った職人の確保が難しくなっています。
また、働き方改革の推進により、長時間労働の是正や有給休暇の取得促進などが求められ、これらも人件費上昇の要因となっています。
さらに、2020年に開催予定だった東京オリンピック・パラリンピックの関連工事により、建設需要が一時的に高まったことも人手不足に拍車をかけました。
これらの要因が重なり、建設業界全体で人件費が上昇し、結果として新築住宅の価格高騰につながっています。
このように、建設業界の構造的な問題と社会的要因が複合的に作用し、人件費の上昇を通じて新築住宅の価格高騰を引き起こしています。
今後、この問題を解決するためには、生産性向上や人材育成、さらには外国人労働者の活用など、多角的なアプローチが必要となるでしょう。
新築住宅価格高騰の落ち着く時期

新築住宅価格の高騰が続く日本ですが、今後価格が落ち着いてくるタイミングも知りたいものです。
ここでは、新築住宅価格が落ち着いてくる時期の特徴を解説します。
◉ 税制改正が行われたタイミング
日銀による金利引き上げ時
新築住宅価格の高騰が落ち着く可能性が高いのは、日本銀行が金利を引き上げた時です。
近年の住宅価格高騰は、長期にわたる低金利政策が一因となっています。
低金利環境下では、住宅ローンの借入れが容易になり、住宅需要が刺激されます。
また、投資家にとっても不動産投資の魅力が高まり、複合的に作用して価格上昇を招く仕組みです。
一方で日銀が金利を引き上げると、住宅ローンの金利も上昇し、住宅購入の負担が増加します。
これにより、住宅需要が抑制され、取引量が減少。同時に、不動産投資の魅力も相対的に低下するため、投資目的の購入も減少傾向になります。
結果的に住宅価格の下落につながります。
ただし、金融政策の変更は経済全体に大きな影響を与えるため、その実施には慎重な判断が必要です。
住宅市場の動向を注視しつつ、適切なタイミングでの政策変更が求められるでしょう。
税制改正が行われたタイミング
税制に関する法律改正が策定された場合、住宅価格の安定につながる場合があります。
不動産取引を促進するための様々な税制優遇措置があるからです。
例えば、住宅ローン減税や、相続した空き家の譲渡所得の特別控除、登録免許税の軽減措置などが挙げられます。
税制優遇措置は、不動産市場を活性化させ、取引を増やす効果につながる可能性があります。
一方で同時に需要を喚起し、価格を押し上げる要因にもつながります。
仮に税制優遇措置が縮小された場合、不動産取引の需要は減少傾向に転じる可能性が高いです。
需要の減少は、取引件数の減少につながり、結果として価格上昇圧力を弱めることになります。
特に住宅ローン減税のような大規模な優遇措置の見直しは、市場に大きな影響を与えます。
不動産取引を活性化させる税制の見直しは、新築住宅価格の高騰を抑制する効果が期待できます。
新築住宅が高いと感じた時に予算内でより良い家を建てる方法

新築住宅が高いと感じる方は多いのではないでしょうか。
ここでは予算内で理想の住まいを手に入れるための方法を解説します。ぜひ参考にしてください。
◉ 中古住宅を購入しリノベーションを実施
新築住宅ではなく中古住宅を選ぶ
予算内で理想の住まいを手に入れる方法のひとつが、中古住宅を選択することです。
中古住宅を購入し、リノベーションを行うことで、新築住宅よりも安い価格で魅力的な住まいを手に入れることができます。
中古住宅は基本的に新築よりも安価です。またリノベーション費用を含めても新築住宅よりも価格は低いです。
さらに、中古住宅のリノベーションは環境にも配慮した選択肢です。
既存の建物を活用することで、新築に比べて資源の無駄を減らし、環境負荷を軽減することができます。
古い建物の味わいを活かしながら現代的な機能を付加することで、独特の魅力を持つ住まいを作り出すことも可能です。
中古住宅の購入とリノベーションを組み合わせることで、予算内でより良い家を手に入れる選択肢が広がります。
新築にこだわらず、中古住宅の可能性を探ることで、理想の住まいづくりを実現できる可能性が高まるのです。
【2025年最新】リノベーション会社が手掛けるおしゃれな事例13選を紹介
中古住宅を購入しリノベーションを実施
中古住宅を購入してリノベーションを行うことで、予算内でより良い家を手に入れることができます。
この方法の最大のメリットは、新築住宅よりも大幅に安い価格で、自分好みにカスタマイズした住まいを実現できることです。
また、立地条件の良い物件を選ぶことも可能になり、新築では難しい好立地での暮らしを実現できる可能性が高まります。
古い建物の味わいを活かしながら現代的な機能を付加することで、独特の魅力を持つ住まいを作り出すことも可能です。
中古物件選びからリノベーションまで仲介手数料無料の「リノデュース」
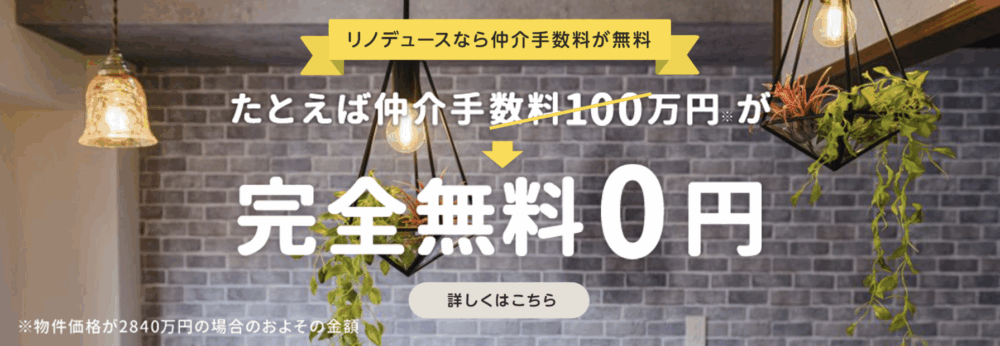
リノデュースでは、物件選びのプロがリノベーションに適した物件を厳選し、お客様のライフスタイルや将来設計に合わせた最適な選択をサポートします。
さらに、物件購入後には、経験豊富な職人たちが高品質なリノベーションを行い、理想の生活空間を創造します。
物件探しから設計、施工までを一貫したワンストップ体制でサポートするので、お客様は安心して理想の住まいづくりを進めることが可能です。
リノデュースの大きな魅力は、仲介手数料が無料であることです。
物件購入時の初期費用を抑え、その分をリノベーション費用に充てることで、予算内で最大限に理想の住まいを実現できます。
実際のリノベーションの雰囲気や素材感を確かめたい方は、ショールームも開催しているので、お気軽にお越しください。
動画で具体的な事例をご覧になりたい方は、以下のYouTubeチャンネルもぜひご参照ください。
リノベーションとセット購入で
お得に理想の住まいを
実現しませんか?
- 今なら中古購入+リノベで仲介手数料0円!
- 完全オーダーメイドで理想の住まいを実現!
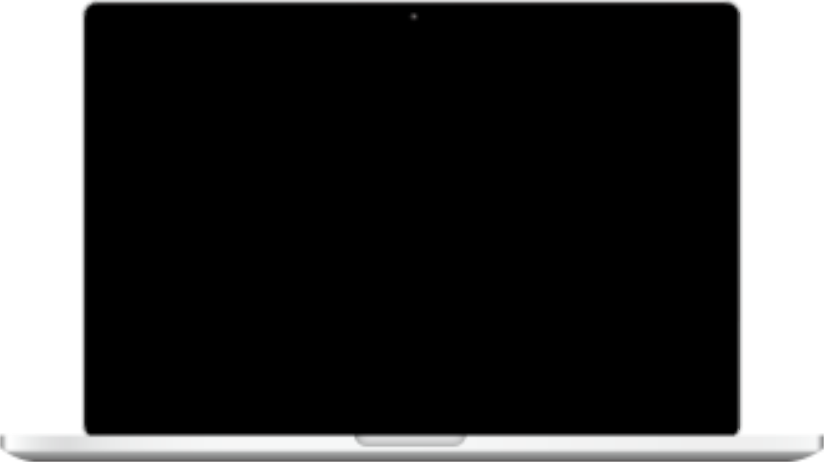
- 今なら中古購入+リノベで仲介手数料0円!
- 完全オーダーメイドで理想の住まいを実現!
中古住宅や土地の価格推移も紹介

新築住宅の価格が上昇していますが、中古住宅や土地の市場も活発です。
建築資材や人件費の高騰という共通の要因に加え、中古市場特有の需給バランスも価格に影響しています。
ここでは、中古住宅と土地それぞれの価格推移について、特徴と傾向を詳しく解説します。
◉ 中古一戸建ては全体的に上昇傾向
◉ 中古マンションも11年連続で上昇
土地は下落した年はあるものの直近は過去3年を上回る
首都圏における100〜200平方メートルの土地成約価格は、過去10年間で下落した年もあるものの、全体的には上昇傾向にあります。
特に直近3年間は前年を上回る上昇が見られ、この傾向は首都圏の各都県で共通しています。
土地価格の上昇は住宅価格全体を押し上げる大きな要因であり、その背景には海外投資家の参入、全国的な地価上昇、そして三大都市圏でのホテルやマンション需要の高さなどが考えられます。
以下に、公益財団法人東日本不動産流通機構の調査に基づく、首都圏における100〜200平方メートルの土地成約価格の推移を示します。
| 年 | 価格(万円) | 1平方メートル当たり単価(万円) | 1平方メートル当たり単価前年比(%) |
| 2013 | 2,849 | 19.82 | 1.7 |
| 2014 | 2,792 | 19.42 | -2.0 |
| 2015 | 2,747 | 19.07 | -1.8 |
| 2016 | 2,796 | 19.30 | 1.2 |
| 2017 | 2,842 | 19.62 | 1.7 |
| 2018 | 2,904 | 19.97 | 1.8 |
| 2019 | 2,897 | 19.96 | -0.1 |
| 2020 | 2,810 | 19.41 | -2.8 |
| 2021 | 2,948 | 20.41 | 4.8 |
| 2022 | 3,397 | 23.47 | 15.0 |
| 2023 | 3,529 | 24.37 | 3.8 |
引用:公益財団法人東日本不動産流通機構 首都圏不動産流通市場の動向(2023年)
中古一戸建ては全体的に上昇傾向
首都圏の中古一戸建て価格は、土地と同様に過去10年ほど全体的に上昇傾向です。
前年比で価格が下がった年もありましたが、2021年と2022年は特に大きく上昇し、2023年もその傾向が続いています。
この価格上昇は、物件の広さや築年数だけでは説明できません。
同じ調査によると、過去10年間に取引された中古一戸建ては、平均的な土地面積や建物面積が小さくなり、築年数も古くなっているのに、成約価格は上がっています。
背景には、中古物件への高いニーズ、リフォームを希望する人の増加、新築価格が高いために中古物件に注目が集まるなど、さまざまな理由が考えられます。
なお、公益財団法人東日本不動産流通機構の調査による首都圏の中古一戸建て成約価格の推移は、以下の通りです。
| 年 | 価格(万円) | 前年比(%) |
| 2013 | 2,921 | 0.1 |
| 2014 | 2,917 | -0.1 |
| 2015 | 3,011 | 3.2 |
| 2016 | 3,030 | 0.6 |
| 2017 | 3,072 | 1.4 |
| 2018 | 3,142 | 2.3 |
| 2019 | 3,115 | -0.9 |
| 2020 | 3,110 | -0.2 |
| 2021 | 3,451 | 10.5 |
| 2022 | 3,753 | 8.8 |
| 2023 | 3,848 | 2.5 |
引用:公益財団法人東日本不動産流通機構 首都圏不動産流通市場の動向(2023年)
中古マンションも11年連続で上昇
首都圏の中古マンション市場では、成約価格と1平方メートルあたりの単価が11年連続で上昇し、価格高騰が顕著です。
過去10年間を見ると、中古マンションの平均専有面積はわずかに減少し、平均築年数も約4年増加しているにもかかわらず、成約価格は約2,000万円も上昇している点が特徴的です。
その背景には、都心部への人口集中や共働き世帯の増加に伴う利便性の高い場所へのニーズの高まり、新築マンション価格の高騰による中古物件への需要の移行、不動産投資マネーの流入などが複合的に影響していると考えられます。
さらに、金融緩和によるインフレの進行も不動産価格を押し上げる要因の一つです。
なお、以下に公益財団法人東日本不動産流通機構の調査に基づいた、首都圏における中古マンションの成約価格の推移を示します。
| 年 | 価格(万円) | 1平方メートル当たり単価(万円) | 1平方メートル当たり単価前年比(%) |
| 2013 | 2,589 | 39.96 | 4.7 |
| 2014 | 2,727 | 42.50 | 6.3 |
| 2015 | 2,892 | 45.25 | 6.5 |
| 2016 | 3,049 | 47.92 | 5.9 |
| 2017 | 3,195 | 50.00 | 4.4 |
| 2018 | 3,333 | 51.61 | 3.2 |
| 2019 | 3,442 | 53.45 | 3.6 |
| 2020 | 3,599 | 55.17 | 3.2 |
| 2021 | 3,869 | 59.81 | 8.4 |
| 2022 | 4,276 | 67.24 | 12.4 |
| 2023 | 4,575 | 71.90 | 6.9 |
引用:公益財団法人東日本不動産流通機構 首都圏不動産流通市場の動向(2023年)
今後の住宅価格推移の動向と売買のタイミング

住宅の購入や売却を考えている人が、「今買うべきか」「いつ売るのがベストか」と悩むのは当然です。
住宅ローン金利や建築費の高騰など、情報が入り乱れ、見通しを立てにくい状況です。
ここでは、社会情勢や市場の動きを踏まえ、今後の住宅価格がどうなるか、購入・売却の最適な時期はいつか、について解説します。
◉ 売却はタイミングを逃すとリスク増加
購入するなら早めの行動がベスト
現在、円安傾向が続いており、アメリカの利下げが当初の予想より遅れていることから、この状況はしばらく続くと見られています。
さらに、ウクライナ情勢の長期化や中東の地政学的リスクの高まりが原油価格を押し上げ、建築資材や輸送コストの上昇につながっています。
そのため、2025年に入っても建築費は高止まりの状態が続いています。
不動産価格を見ると、2024年後半から2025年前半にかけて、地方都市や郊外を中心に価格が横ばい、またはわずかに下落する地域が出始めています。
ただし、都心部や再開発エリア、インバウンド需要が見込める地域では、依然として高い価格を維持しています。
つまり、全国的に明確な下降とまでは言えませんが、価格上昇の勢いは弱まっていると言えるでしょう。
また、2025年春以降、住宅ローン金利は徐々に上昇しています。
金利がさらに上昇すると、毎月の返済額が増え、借入できる金額が減る可能性があります。
「物価が落ち着くまで待とう」と考えていると、金利上昇によって住宅取得にかかる総費用が増加してしまうリスクがあります。
そのため、近い将来、住宅の購入を検討している場合は、早めに動き出すことが有利になることもあります。
売却はタイミングを逃すとリスク増加
価格が上昇している間は売却を控えるという考え方もありますが、2025年の市場では、都市部を除き、一部地域で価格の伸び悩みや横ばい傾向が見られます。
売却を検討する上で重要なのは、築年数が経つにつれて建物の価値が下がっていくという点です。
特に築20年、30年を超えると建物の資産価値は大きく目減りし、土地の値段だけで売却される「古家付き土地」となるケースも増えています。
さらに、2025年に入ってから住宅ローン金利は徐々に上昇しており、今後も上がる可能性があります。
金利が上がると、購入希望者のローン負担が増すため、これまでの価格では売れなくなるおそれがあります。
つまり、売却のタイミングを逃すと「築年数による価値の低下」と「金利上昇による購入者減少」が重なり、売却価格が下がるリスクが高まります。
数年以内に売却を考えているのであれば、価格が比較的高いうちに、かつ金利が大きく上がる前に行動するのが理想的です。
新築・中古住宅の価格推移を見極めベストなタイミングで不動産売買を行おう

この記事では、新築の価格推移について解説してきました。
近年、建築資材や人件費の高騰、円安、金融緩和などを背景に、新築住宅の価格は上昇傾向にあります。
特に新築分譲マンションは全国平均で11年連続、1平方メートルあたりの単価も7年連続で上昇し、過去最高値を記録しました。
中古住宅や土地も同様に価格が上昇しており、土地は直近3年、中古一戸建て、中古マンションは10年以上にわたり上昇傾向が続いています。
今後の住宅価格は、円安の継続や建築費の高止まり、住宅ローン金利の上昇が見込まれるため、住宅購入は早めの行動が有利です。
一方、売却は築年数による価値の低下や金利上昇のリスクを避けるため、タイミングを逃さないことが重要です。
もしリノベーションを視野に入れた住宅選びなら、「リノデュース」がおすすめです。
物件選びのプロがリノベーションに適した物件を厳選し、経験豊富な職人による高品質なリノベーションを、中古マンション選びから設計・施工まで仲介手数料無料のワンストップサービスで行います。
そのため、ご希望の予算内で高品質な生活空間を実現できます。
また、東京や埼玉でショールームも随時開催しております。実際の雰囲気や素材感をぜひご体験ください。
リノベーションとセット購入で
お得に理想の住まいを
実現しませんか?
- 今なら中古購入+リノベで仲介手数料0円!
- 完全オーダーメイドで理想の住まいを実現!
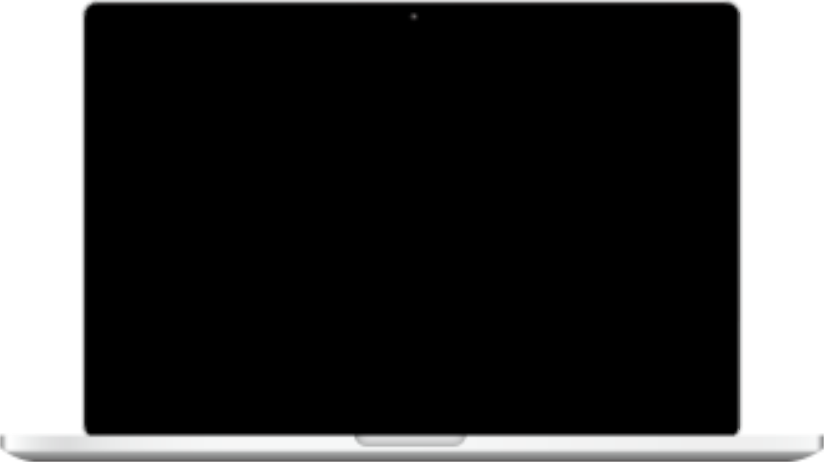
- 今なら中古購入+リノベで仲介手数料0円!
- 完全オーダーメイドで理想の住まいを実現!